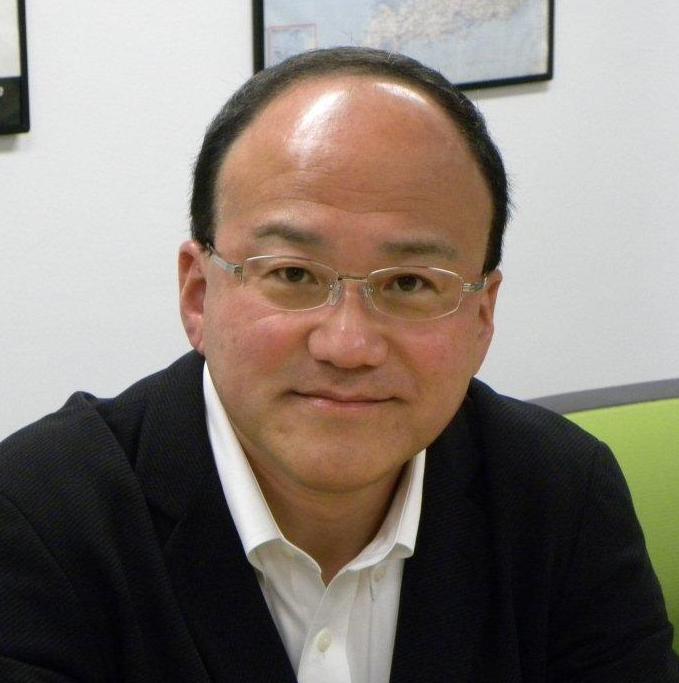活動報告
『半年ギャップイヤーの捉え方-大学は今何を検討すべきか-』セミナーレポート
2012年6月7日(木)16時より、TKP東京駅丸の内会議室において、大学の明日を考える会・秋季入学移行問題・論点整理セミナーを開催しました。
講演会の内容は次のとおりです。
1.開会の辞・講師紹介 理事長 大橋 光博
2.講演
「大学教育現場で、なぜ今ギャップイヤー導入なのか
-秋入学との論点を踏まえて-」
砂田薫 氏
一般社団法人 日本ギャップイヤー推進機構協会 代表
3.質疑応答
講演の主なポイントは以下のとおりです。
ギャップイヤーとはもともと、1960年代の英国で生まれた「良き慣習」だった。それが今、世界の状況に合わせ、高等教育における、人材育成ツールの"サイエンス"として考えられるようになってきた。英国ではおおよそ18-25歳がその対象であり、大学入学前の16ヶ月間を使って見聞を広めよう、というところから始まった。現在、英国にはギャップイヤーの支援を行うNPOや株式会社が多数あり、大学生、社会人のおよそ2割がギャップイヤーを経験していると言われている。特にベルリンの壁崩壊以降は、航空券が安くなったということもあり、ギャップイヤーを経験する若者が増えて、"ギャッパー"という言葉も生まれた。
ギャップイヤーは、必ずしも海外留学をしなければならないということはなく、国内留学やインターン、ボランティア、アルバイト、その他レジャーもギャップイヤーの一部である。よって大変広汎な意味を有するが、それを日本の教育現場で考えた場合、コンセンサスを得るのは、(1)インターン、(2)ボランティア、(3)課外国内外留学の三つであると考えられる。
東京大学が全学科の秋入学移行を発表したことで、ギャップイヤーをめぐる情勢は大分変わってきた。今年4月には、経産省が大学生に、50-100名の規模でインターンの予算をつけることを発表。また、朝日新聞の主催で親子向けのギャップイヤーセミナーも行われ、広く認知を促す動きが進んでいる。学生の意欲低下、大学システムの不足などが盛んに言われているが、これらは今や、産官学の専門家だけではなく、"民"も一緒に考えるべき問題であろう。
"グローバル人材"に求める資質は、日本でも海外でもほとんど変わらない。そしてギャップイヤー制度は、現在求められている国際的な応用力、創造力を重視した教育と親和性が高いのである。例えば、2010年の世界教育心理学界では、オーストラリアにおける高校卒業後の学習意欲とその成績の関係調査において、ギャップイヤーを経験した大学生の方が就学後のモチベーションが高く、企画力、忍耐力、時間管理能力などが高いことが統計的に立証された。
文系理系問わず、何らかの社会奉仕活動をした経験、あるいは人並み外れた情熱をもって何かに取り組んだ経験を持っている者を評価する風潮がアメリカや英国にはあるが、日本人は得てして、トコロテン式に高校から大学まで、間を空けずに進学するべきだという考えにとらわれがちである。一方で、世界的に見ると大学進学率はそう高くないという現実がある。特に25歳以上の進学率は各国と比べて非常に低い。
大学というのは、純粋な研究・教育・就学機関であるというのがこれまでの基本的な考え方だったが、東大はここに新たに、就労体験や社会体験という要素を、必要条件として加えた。これはつまり、高等教育の人材育成が、「正課目+課外活動(本格的社会体験と就業体験)」のトータルなものであるべきだと、東大が認めたということである。高等教育に、産官学だけでなく、「民」が関与していくべき時代の到来と言える。現在、秋入学導入に関する企業の採用活動意識調査などでは、選考時に「参考にする」企業が58%と、実に6割近い企業がギャップイヤーの経験を評価する意向を示している。
ギャップイヤーの検討課題としては、行政、家庭それぞれでの経済的負担の増大や、「空白期間」に対する社会の偏見の目、単位認定・認証のあり方の検討不足などがある。これらについてはまだ、今後の大学の構造改革、支援団体によるビジネスモデルの確立など、様々な試みを要する段階ではあるが、いずれにしろ、これらの問題提起は、大学という機関の在り方を皆で議論する良い機会となるはずである。
ギャップイヤーは海外の制度だと言われがちだが、「かわいい子には旅をさせろ」「他人の窯の飯を食う」などの格言があるように、日本にも、親元を離れ非日常を経験することを、成熟への道のりの一つと考える概念はある。少子高齢化の時代にあたり、数の少ない若者たちには今後多くの、そして丁寧なケアが必要となってくる。ギャップイヤーを通じて、彼らがより動きやすく、より多彩な経験を積むことの出来る場を提供していきたい。
セミナー内容 以上